その女性は、密かにブループリンスと呼ばれていた。 まだ彼女が目覚める前、彼女は”王子様”と呼ばれていた。 けれど、彼女が目覚めた時、ずっと閉じられていた瞼の下から現れた、あまりにも青く 澄んだ美しい瞳によって、彼女はそう呼ばれた。 そう呼ばせるだけの美しさが、彼女にはあったのだ。 そして、だれも彼女の本当の名前を知らされていなかったのだから。 |
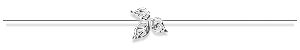
ブループリンス
その女性は、密かにブループリンスと呼ばれていた。 まだ彼女が目覚める前、彼女は”王子様”と呼ばれていた。 けれど、彼女が目覚めた時、ずっと閉じられていた瞼の下から現れた、あまりにも青く 澄んだ美しい瞳によって、彼女はそう呼ばれた。 そう呼ばせるだけの美しさが、彼女にはあったのだ。 そして、だれも彼女の本当の名前を知らされていなかったのだから。 |
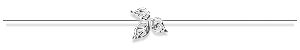
重い瞼を開かせたのは、静かな空気を振るわせる電子音。 ………何かが聞こえる。 …何の音? 私はいつ、どこで眠ったのだろう………? ここは………どこだ………? うっすらと目を開くと無機質な白い天井が目に入り、ようやくそこが病院であることが わかった。 「気が付きましたか?わかりますか?ここは病院ですよ」 すぐ傍らから女性の声がした。 借り物のように自分自身の体が重く、目覚めたばかりの脳は告げられている言葉の 意味を理解するのに時間を要した。 静かに、でもしっかりと手の先を握られて、僅かに力が戻ってきたように感じる。 何とか声のしたほうへ顔を向け、頷いて見せたが、眠りから覚めたばかりの脳は ぼんやりと霞が掛かっているようで、全てが曖昧だ。 なぜ、こんなところへ……? はっきりしない脳裏を掻き分けるようにして記憶を辿る。 そうだ、面会に行ったのだ、自分は。 そして?…思い出せない。そして……。 会えなかった………、兄に、いつもの通り。 会いたい。 思考回路は現から程遠く、夢の中を彷徨い、誘われるように薫は再びその瞼を閉ざした。 会いたい、会いたい………会いたい。 ……会えない………。 |
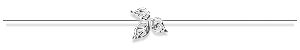
「まだ、わからないのですか?彼女の身元は」 事務局長は、途中報告をもってきた刑事に開口一発、文句をつけた。 「そう言われましても、こちらは捜索願が出されたものを中心に当たるしかないものです から……」 身元不明の美しい女性が運び込まれたのは、もう4日も前のことだった。 東京拘置所のすぐ傍らで倒れていた女性だ。 本人はまだ意識が戻らない。状況からして、脳に障害が残る可能性も捨てきれない。 それなのに、未だにその身元がわからないのだ。 様子からして、20代前半と思われる若い女性。 身につけていたのは高級品ばかりで、その歳の女性にしては多額の現金も持っていたが、 身元に繋がるものを、何一つ持っていなかったのだ。 キャッシュカードもクレジットカードも、もちろん運転免許証も。 それどころか、普通なら一枚くらいは見つかりそうなショップの会員カードもスタンプカードも、 何一つ。 ブルガリの財布の中に収められていたのは、現金のみ。 病院はすぐに警察に届け出たが、それらしい人物は見つからなかった。 そんな人間をいつまでも預かっていくわけにも行かないし、かといって意識不明の病人を 追い出すわけにもいくまい…。 事務局は対応に困り果てて頭を抱えた。 |
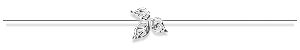
一般病棟に移された薫は、ぼんやりとただ白い天井を眺めた。 相変わらず、部屋の中には心電図の音だけが規則的に響いていた。 単調な電子音が、取り留めのない思考の邪魔する。 まるで精彩を欠いた瞳は、ただただ白い天井を見つめるのみ。 薫は自分の居所を改めて思いやった。 都立綾瀬川病院。 拘置所のすぐ近くの病院だ。駅に大きな看板があったはずだ。 そこまで来て、ようやく考え付いた。 拘置所のすぐ近くにいるのだ。兄のすぐ近くに……。 そう思うと、居ても立ってももいられなかった。自分に繋がる全ての医療用の管を 引きはがして、這いずるようにしてベッドから窓辺に向かう。 歩く、そんな立派なものではなかった。 当然だ。CCUから一般病棟に移されても、ずっと絶対安静のままで身体を起こすことさえ 短時間だったのだから。 そんなことさえ気にせずに、薫は倒れこむように窓に向かって、カーテンを引いた。 その向こうに見えたのは…。 とうきょうこうちしょ。 兄のいる。拘置所の見える場所に、自分はいるのだ。 ………会いたい、会いたい。 こんなに近くにいるのに…会えない…。 なぜ…。 自然と涙が溢れていた。 会いたいのに会えない。このまま一生、会えなかったら………。 考えると、全身が戦慄した。ふっと呼吸が苦しくなる。 間近にいる、こんなに近くに………。なのに、会えない。 「何をしているんですかっ?」 背後から、叫びに近い声が投げかけられた。 その声もぼんやりと頭の中にこだまし、届かないまま、薫は床に倒れこんだ。 倒れこんだ床の冷たさだけ、認識することができた。 ………あなたのいる部屋も………床はこれ程冷たいのですか? 声を聞かせて、その冷たさを教えて…。 その哀しみを、共有ことすら許されないのでしょうか? なぜ………。 |
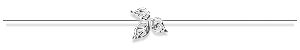
特別室の”ブループリンス”の点滴の準備を終えて、ワゴンを押す。 CCUで意識不明のまま1週間。何度か危篤状態にも陥ったが、何とか意識を取り戻し、 危惧していた後遺症も残らなかったのは、本人にとっても病院にとっても 幸福なことだった。 さらに3日をCCUで過ごし、状態が安定した今は、一般病棟に移されている。 “ブループリンス”は彼女のあだ名だ。身元不明で名前がわからなったから、 ナースがそう呼び始めた。 彼女の青く見えるほど澄んだ瞳と、名を伏せたまま特別室に移された権力に、 その名が冠せられた。 しかし、あまりの美しさは、病院内に波紋を広げた。 まだ彼女がCCUに収容されていた時、順繰りにナースが彼女の傍に張り付き、 結果として他の患者からクレームがついて、救急の婦長が引責辞任するまでに なったのだ。もちろん、彼女が一般病棟に移ってくるときには、誰が主担当を勤めるかで 揉めに揉めた。 彼女の担当を任されたのは、内科に転任してきたばかりの円だった。 なんで新人の円がと、その選考には内科のナースの不満を買った。 なんで皆、わからないのよ。 内科的知識には、勝てない。 でも、5年間、精神科を担当してきた人間にならわかる。 あれは生きる気力のない人間の目だ。 皆が艶めかしいと絶賛する瞳が、けれど虚ろに輝き、遠くを見つめ、それが何より危険な 精神状態を物語っていた。 形ばかりのノックをして、静かに戸を引く。 部屋に入った瞬間、思わず立ち止まってしまい、反応が遅れた。 まだまだ修行が足りないと思う。 絶対安静のはずのプリンスが窓辺に立っていた。 「なにやっているんですか!?」 思わず声を張り上げたが、プリンスは振り返ることなく、円の目の前で崩れるようにして 床に倒れた。 「プリンス!」 |
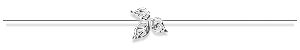
CCUで意識を回復した時、最初に尋ねられたのは、自分の身元だった。 カードを収めたケースを寮に忘れてきたのだ。 捜索願なんて、出されているはずもない。 なぜなら、祝日と日曜日の3連休に文化祭後の休暇に合わせて6日間の帰宅届を寮に 出していたのだ。 学校は、自宅にいると思っているだろう。 それに響谷の家に帰るときに、わざわざ連絡をいれたことだってない。 響谷の家は、寮にいるとばかり思っていたことだろう。 自分がいないことに誰かが気付くのは、もう少し先のはずだ。 病院側から問いただされた身元については答えていない。 ……なぜ、なんて理由はない。 響谷薫であることの意味が何もなかった。 響谷の家の中で幸せな時間をともに過ごした兄はもういない。 響谷薫の名で面会に行って会えることもない。 バイオリンさえ、響谷薫の名で弾くことがないのだ。 名前なんて、もう自分には必要ない。 だから名前なんて必要ない。そんな名前でなど呼ばれたくない。 必要だったのは、この部屋にいることだけ。この場所にさえいられれば、他にはなにも いらない。 名前なんて必要ない。 だから、一切口を開かなかった。 響谷家の執事を呼び出して、入院の手続きだけをさせた。 名前も住所も伏せたまま。 彼はあれで、顔が広い。病院の上部か関係官庁にでも手を回したのだろう。 でなければ身元不明の人間が、特別室などには入れないだろう。 それくらいのことは、自分にでもわかる。 どうせ民事訴訟で支払った賠償以外に、使うあてなどない響谷の金だ。 勝手にどうとでも使えばいい。 |
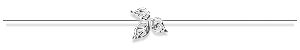
「君らはいったい何を見ているんだねっ!」 プリンスの状態が安定すると、まず真っ先に担当医から叱責を受けた。 当然と言えば、当然だ。 とうてい動ける状態ではない患者が立ち歩き、危険な状態にしてしまったのだから。 「申し訳ありません」 「謝って、患者の命が戻ってくると思うな!起こってから反省したって遅いんだ!」 ぐっと拳を握り締めて、悔しさを堪える。 もう少し気付くのが遅れていれば、本当に彼女の命はなかったかもしれない。 そういうことだ、一人の重症患者を担当するというのはそういうことだ。 「………な、よ」 微かな声が耳に入って、担当医と共に振り返る。意識を取り戻したプリンスの声だった。 「ダメよ、マスクを戻して」 酸素マスクを取り外し、まっすぐにその瞳は医師を見すえていた。 もう一度マスクを填めようとした私の手を、震える冷たい手で制しながら、プリンスは声を 絞り出す。 たちまち唇から血の気が失せていく。私は指示を求めて医師を振り返った。 「なんだね?」 仕方ないと言ったように医師がプリンスの元へと歩み寄る。 「それくらいに、しておいてやりなよ」 喘ぐような息を整えるように、何度か大きな呼吸を繰り返して、一生懸命に声を絞り出す。 「四六時中、ついていられるわけじゃ、ないだろう…。ナースを責めて、どうする? バ…カ……じゃ、ないの……か………」 「なんだと!?」 怒りを露にした医師に、薫は嘲るように微笑んだ。 「だから、それ…くら…い、に………」 続きは聞こえなかった。 苦しげに、その端整な美貌が歪んで、大きく身体をよじるようにして反転する。 同時に、大きく心電図の波形が乱れる。 「今度から、死にたがる患者を私のもとには連れてくるな、不愉快だ」 冷酷にさえ聞こえる声音で、医師が呟いた。 |
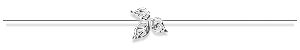
何度、断られただろうか。 思い返せば、きっと回数を数えることができるはずだ。 それをしなかったのは、自分の心を守るため? 認識してしまったら、きっと自分はそこで壊れてしまう、バラバラになって内側から。 今日こそ会ってくれるだろうか、そんな淡い期待さえ持てなくなって……。 それでも足を運ばずにはいられずに、通っては断られ、また同じ道を引き返す。 それが習慣になってしまいそうだった。 ほんの僅かな時間だけでも会話を交わせる幸福の場所は、もう二度と見たくない絶望の 場所へと取って変っていた。 「響谷巽の意思により、面会はできません」 あぁ、ほら。やっぱりだ………。 その日もまた、拘置所を背にして来た道を引き返す。 秋の澄んだ青空の下で、官舎には気持ちよさそうに洗濯物がはためいている。 うっとおしいほどの熱気を持っていた風は、次第に涼しさを増し、いつの間にか冷たさを 感じるようになっていた。 ………拘置所の中はどれほどに寒いのだろう………………。 なぜ哀しみを共有することを許してはくれないのだろう。 薫は拘置所の塀に沿って裏手へ周ってみた。 殺風景な建物。 ふっと瞳を閉じて、薫は自宅の部屋を思い出していた。シックに纏められていた兄の部屋。 それでも温かみのあった部屋。 今は、どれほどに寒い部屋に彼はいるのだろう………。 それとも、新しい彼女がいて、そんな寒ささえ感じることはないのだろうか…? 教えてよ、声を聞かせてよ……少しでいいから。 コツンとコンクリートの塀に額をつけた。 じんとその冷たさが額に伝わり、熱い涙が頬を伝う。 胸が苦しくて、その胸を押さえた。 自分の身体を支えきれず、薫はアスファルトに目一杯膝を打ち付けて、そのまま 倒れこんだ。 …打ち付けた膝が痛い。 ……アスファルトで擦った手が痛い。 ………心臓が痛い。 …………傷ついたこころが……いたい。 助けて、昔みたいに、兄のままでいいから………抱きしめて………。 薫はその苦しさに絶えられず、ゆっくりと瞼を閉じ、意識を手放した。 華奢な手からカツンと音を立ててケースが落ち、ニトロの錠剤がアスファルトの上に いくつか散らばった。 ねぇ、聞こえないの? あたしの声が、聞こえないの………? |
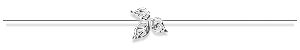
ゆうらりと、薫は瞳を開いた。 既に夜だった。 ヘッドライトに照らし出された、病院特有の白い天井が目に入る。飾り気のないそれが 薫に拘置所を思い出させた。 もっと暗いに違いないグレーのコンクリートに囲まれた部屋。 たちまち涙があふれ、耳元をつたって流れ落ちる。 会えないまま彼を失うのならば、自分が先にいってしまいたい。 それならば、会えない哀しさも、彼を失う恐怖にも耐えずに済むのだから。 でも、ここなら見ていられる。 図らずして、彼の見えるこの場所に来てしまった。 彼の住む場所を、毎日見ていられるのだ。 「何を、考えているの?」 無人だとばかり思っていたのに、すぐ近くから声を掛けられて、薫はどきっとして視線を 向けた。 黒い髪を無造作に纏め上げた担当のナースだった。 「……何も」 涙を隠すように左手で顔を覆った。 「それよりも、もう勤務時間は終わっているんだろう?こんなところで何をしているんだい?」 制服ではなく、スモークピンクのオフタートルのセーターにツィードのスカート。 あぁ、と自分の姿を見て、微かにナースは微笑んだ。 「無茶をして、なかなか目を覚まさないから………せめて、あながが目を覚ますのを 見届けて帰ろうと思ったの。怒られたしね、気を使うに越したことはないわ」 「責任の在処はあたしだよ?ナースを責めて解決しないと言っただろうに」 本当に呆れたと行った様子で、プリンスは呟いた。 達観した物言いが、いやに大人びていた。もしかしたら私が思うより、年をとっているのかも しれない。 「ねぇ、本当は幾つなの?」 まず、肌を見たときに若いなと思った。 10代のような滑らかさで、くすみ一つない色白の肌は、赤ちゃんの肌みたいに肌理が 整っていた。 けれど、その瞳の翳はとても大人びていて、彼女の年齢を不明にしていた。身につけてる モノからすれば、大学生かOLかといった所かな。 「17歳」 想像を膨らませていたところに、あっさりとプリンスから答えが返された。 意外な若さに、思わずベッドのなかのプリンスを見下ろした。 「何、意外?」 「だって、ニット、アルマーニだったよ?」 私のセリフが、あまりにとぼけたものだったのか、プリンスはあからさまにため息を付いて、 小ばかにしたような笑みを浮かべた。 「別に、服で年齢が決まるわけじゃないだろ。それとも何?17に見えないとでも?」 見上げてくる瞳は、艶かしくて、思わず見とれてしまう。その瞳が、17歳のものとは とうてい信じられない。 心の奥底を見透かされているようで、そこに彼女の深みを感じるのだ。 「見えない。OLかと思ってた……。でも、フツーのOLじゃ、あれだけのものも持てないか…」 彼女の暗い翳を宿した笑みは、まるで私が想像する高校生のものとはかけ離れていた。 彼女の所持品一つとっても、高校生が持つには高級すぎるものばかりだった。 もちろん、プリンスがそれを身に付けたところを見たわけではないけれど、きっと素晴らしく 似合うに違いなかった。一般のOLには、とても着こなせない上質のモノ。 「ふーん……。ま、どっちでもいいけど」 言いながら、プリンスは細い手を伸ばして、ベッドサイドに置いてある腕時計を取り上げる。 元々興味がないので、型などはわからないけれど、それがブルガリであることくらいは、 私でもわかる。 ジャラリと音を立てて時計を置くと、またプリンスはため息を付く。 「おいおい、こんな時間になって、どうするつもりだい?帰れるのかい?」 慌てて自分の安物の腕時計に目を落とす。 既に深夜の2時を差している。 「あぁ、ホント。ちゃんと休むのよ」 「あたしじゃなくて、あんたが。帰れるのかって聞いてるんだよ」 プリンスの瞳にはいつも人を小ばかにしたような嘲笑が浮かんでいるけれど、 今はそんなんじゃなかった。 プリンスは優しいのかもしれない。さっきも庇ってくれたし。 責任を押し付けられることはあっても、看護士を庇ってくれる患者なんて、ハッキリ言って 皆無。 なかなか看護士のことを考える患者なんていないの。 それもこんな若くて我侭盛りの年齢の子に。 「うん、慣れてるの。原チャでねすぐだし、明日は休みなの」 眠っている時は、大抵悲しそうな顔をしている。 浅い浅い眠りの中で、プリンスはどんな夢を見ているのだろう。 こうやって起きている時は、自分を隠して笑っているけれど。 眠っている時に、あんなにも哀しそうな顔をしているとは、きっと本人は気付いていない だろう。 何をなやんでいるのだろう。聞いたら、打ち明けてくれるだろうか。 17歳だと言ったプリンスは、それでも年上のあたし達にも何も相談してはくれないだろう。 プライドが高い。人に頼ることを知らない人間だ。 「あなたはまだ顔色が悪いから、ちゃんと眠りなさい」 毛布の襟元を直してやり、囁きかけた。 「早く帰りな。女の子が出歩く時間じゃない」 軽く頷いて見せて、プリンスは更に言った。 あたしは軽く笑いながら、ジャケットを羽織って、マフラーを巻くと、ライトに手を伸ばした。 「お父さんみたいなこと言うね、プリンスは。病人は看護士の心配なんてせずに、 自分の病気を治すことに専念しなさい」 ふっと甘やかな微笑を浮かべて、わかったよとプリンスは低い声で囁いた。 私は小さく手を振って、入るとき同様、静かに扉を閉めた。 扉が閉まる寸前に、泣きそうなほど切なげなプリンスの横顔が見えて、私は悲しくなった。 |
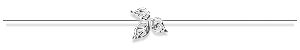
それから2週間は経っていただろうか。 夜勤の日、夕方にナースステーションに入った私は、すぐに異常に気付いた。 随分、慌しい。何かあったのかしら。 「円、プリンスが行方不明になったの!!」 私の姿を見つけた同僚が声を掛けてきた。 「えぇ!?」 散らかりっぱなしのデスクを片付けていた私は、手に持っていたカルテの束を床に ぶちまけてしまった。 「いつもみたいに、中庭や屋上にいるんじゃないの?」 安静となっていても、ふらりとプリンスは病室を出て行くことがあった。 大抵は、屋上や中庭にいる。どんな運動神経をしているのか、高い木の枝に腰掛けて、 ぼんやりと遠くを眺めている。 私はそうであったらいいと思いながら、恐る恐る尋ねた。 勢いよく頭を振って、同僚は否定した。 「いないの。どんなに探しても」 それに、と声を潜めて続けた。 「今日の昼ね、面会人が来て身元がわかったみたいなの。でも、その後に居なくなっちゃって」 「面会人?いつもの人ではなくて?」 身元のわからないプリンスを尋ねてくる人は皆無ではなかった。 毎日プリンスが、皺のないシルクのパジャマを着ているのは、そのおかげだ。 世話人が、ちゃんと面倒を見にやってくる。 「うん……お友達だって…。事務局が撒いたビラ。アレ見て、来たの」 「それからいなくなっちゃったの?………」 一時のことを思えば、プリンスは快方に向かってはいたけれど、彼女は全く薬を飲もうと しなくなっていた。 かわりにアルコールを口にするようになった。 酔って暴れたり、もちろん暴れるほど飲んだりすることはなかったけれど、心臓病の患者が 禁酒の病院でアルコールを飲むなんて、言語道断。 たまに外科病棟で患者どうしでお酒を持ち込んで、怒られてる人もいるけれど、そりゃ、 外科病棟は、身体は問題ないもん。 ただの規則違反。 引き換え、プリンスの場合は違う。 彼女の心臓はボロボロだ。 少量しか食べないプリンスの腕に無理矢理栄養剤を点滴して、安静にさせて、 それが私たちに出来る唯一の治療だった。 「どこにいっちゃったんだろ………。まだ、動き回れる身体じゃないのに…」 私が、呟いたときだった。 「プリンス!」 主任が珍しく大きな声を出した。 見ると、ナースステーション前のエレベーターから、意識を失ったプリンスを両腕に抱えた 少年が降りてくるところだった。傍には小柄な少女が荷物を持って付き添っている。 「ストレッチャーを用意して!」 「大丈夫です、眠ってるだけだから」 主任の指示に動こうとした私を、その少年は止めた。 「重いんで、病室に運んでしまいたいんですけど…」 プリンスを尋ねてきた友人というのは、この少年のことだろうか。 プリンスの顔色は悪かったが、息遣いは穏やかで、確かに危急ではなさそうだった。 私が主任を振り返ると、主任が僅かに頷き、私はもう一度少年に向き直った。 「案内するわ」 「すいません」 小柄な少女が、代わりに言った。 少女は幼い印象だったが、その視線は力強く、しっかりとした表情だった。 黒髪の少年は顔もスタイルも日本人離れしたカッコよさだった。 フロアの一番はしに当たる特別室のドアを引くと、一番に少年が入る。 「しっかし、本当にいやみなほど綺麗な部屋よね。あたしのアパートより広いくらいよ」 少女の愚痴に苦笑いしながら、少年はプリンスの身体をそっとベッドに置く。 そのまま寝かせようとするのを止めて、私はプリンスから上着を脱がそうと手を伸ばした時、 プリンスが瞼を開いた。 ぼんやりと視線を彷徨わせながら、ゆっくりと二度三度、瞬きをした。 「動かないでいいわよ、コート、脱ぎましょう」 焦点の定まりきっていないプリンスにむかって、できるだけゆっくりと、大きな声で 話しかけた。 目が覚めても、彼女の身体はぐったりと少年の腕の中に納まっている。 多分、自分の身体を支えることが出来ないくらいに、衰弱していると想像できた。 プリンスの手は氷のように冷え切っていて、爪の先まで真っ白だった。 「気分は、悪くない?」 袖から腕を抜きながら、私はさらに尋ねる。 目が覚めてきたのか、私のことばに小さく、でもしっかりと頷いた。 少年の手を借りて、プリンスの身体をベッドに横たえると、私はほっと息を着いた。 「ねぇ、まどかちゃん」 弱い声が私を呼んだ。 できるだけ力を使わせないように、プリンスの傍に近寄って、なに?と聞いた。 「退院したいんだけど、明日、準備しといてくれよ」 「………え?」 |
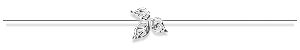
もはや自分が、バイオリンごときで立ち直れるとは、そのときは思っていなかった。 ただ、兄に会えるのだと思うと、弾かずにはいられなかったのだ。 彼の声を、ことばを、欲していた。 久しぶりにバイオリンに触れた。 演奏に集中しようという精神に対し、熱いスポットライトに照らされて、衰弱しきった身体は 悲鳴を上げていた。 引き込まれるような眩暈と息苦しさの中で、音を紡ぐ弓を止めれば、音を取る左手を 止めれば、意識も一緒に手放せるかと考えた。 けれど、兄の面影がそうはさせなかった。 縛られていたのだ、私は。 彼を解放せずに縛り付けていたのが私なら、私をこの世に縛り付けたのもまた、彼だった。 兄の居場所が見えるこの病室でこの世からなくなってしまいたいと、何度思ったことだろう。 いずれ死んでしまう兄に焦がれてこの部屋で過ごすより、自分が彼を待っていたかった。 いつ、開放してくれるのだろう。 私はいつまで頑張ればいいのだろう………。 解放されるべきは、死するとき。 いつ、どちらに、それが訪れるだろう………。 |