〜 2. At RoseGarden 〜
![]()
〜 2. At RoseGarden 〜
オレがファーストクラス専用ラウンジに到着した時には、響谷はすでに来ていた。
ゆったりと腰掛けているソファには黒のコートとヴィトンのパッシィとが無造作に置かれていた。
「早かったんだな」
「今来たことろだよ」
赤みのないこげ茶のロング丈のカーディガンの襟元からは同色のタートルをのぞかせている。
長い足を包むのは、ツィードのワイドパンツだ。
そのグレーのパンツは少しだけ淡い紫の糸が混じっていて、柔らかさを出していた。
カーディガンは上質のカシミアなのだろう、毛足が長くて、薄手でも暖かそうだ。
敬遠しがちなロング丈のカーディガンとワイドパンツの組み合わせも、彼女に掛かると上品で大人っぽい印象で、
むしろそのスタイルの良さが際立つ。
そんな風にパンツをはきこなしても、当然、昔のように男性に見間違うこともない。
オレは、コートを羽織ってパッシィを手にした響谷を想像しててみた。
シックな装いに、イヴォワールのパッシィはさぞ映えるだろう。
コンサートの時にも思ったことだが、響谷は美しくなりすぎていた。
こんなにも女性らしかったなんて思っても見なかった………。
「何?」
立ち尽くしたオレに、響谷は不思議そうに尋ねた。
「いや」
オレは、向かいのソファに座った。
自分のカジュアルすぎる装いを、少しだけ後悔しながら。
「まだ時間がある。しばらくゆっくりしていようか…」
彼女は手元の雑誌に再び視線を下ろした。
長い睫毛が、白い頬に影を落とす。
その透明感のある美しさが、オレは少し怖かった。
あまりに儚く、繊細だったから。
アルディの迎えの車に乗って16区のアルディ本家に着くと、まだ朝早い時間にもかかわらず、
シャルル本人が出迎えた。
「以前に説明したとおり、和矢の手術を先に行う。4日後だ。そのさらに2日後に薫だ。いいね」
説明をしながら、シャルルはアルディの治療室に案内した。
オレたちの部屋は治療室に隣り合う3間続きの部屋で、二部屋の病室と、それぞれの部屋に通じる居間があった。
居間と病室はカーテンで仕切られていて、中央には大きなテーブルと椅子が配置され、食事などは
ここで一緒に取ることができる。
部屋はというと、ダブルベッド並みの広さのベッドと、同じ木目のサイドテーブルのほかにデスクと椅子が配置され、
それぞれの部屋にシャワールームも取り付けられている。
内装は落ち着いたダークブラウンとオフホワイトで纏められていて、唯一ベッドの周りを囲むカーテンだけが
淡いグリーン色に淡いピンク色の花柄で、落ち着いた内装に彩を与えていた。
オレと響谷の部屋の間の壁は可動式で、開け放つこともできるようになっていた。
「和矢はいつもと同じで、手術前は戻る時間と行き先を告げれば、図書室や情報処理室を自由に使ってもらって構わない。
術後はまた様子をみてからだが、おそらく翌日にはある程度の自由は認めてやれるはずだ。
薫は必ず朝の回診のときに申し出ること。体調がいいようなら、車椅子での移動は認める。
ただし、ひとりではダメだ。いいね」
説明しながら、シャルルはオレに一枚のカードを差し出した。
これ1枚で図書室や情報処理室への入室のほか、蔵書の貸出なども全て行える。
3度目となる滞在で、オレはすっかり要領を得ていた。
「今日は夕方に順番に診させてもらう。長旅で疲れてるだろうから、二人ともそれまでゆっくり休むといい。
明後日は季節はずれの暖かさになるとの予報だ。間違いないだろう。
二人で散歩でもするといい、丁度バラ庭園の温室が見頃を迎えているから」
シャルルは、確認するように窓の外に目をやった。
窓から差し込む光を、シャルルの白金髪がキラキラと跳ね返す。
「オッケ」
その光を、少し眩しく思いながら、オレは答えた。
充実した蔵書があるここで、レポートを一本仕上げておきたかったが、響谷と散歩するくらいの時間はある。
「シャルル、今のうちに少し練習しておきたい」
オレの考えとは裏腹に、オレが与えられた部屋に引き上げようとした時、響谷は言った。
オレが振り返ると、案の定シャルルは渋い表情を浮かべた。
当然だろう。
いくらファーストクラスだったとは言え、時差もある。日本からの旅はオレでも少し疲れを感じるくらいだ。
まして響谷の身体ならなおのこと。
現に顔色はあまり良いとは言えず、その表情にも疲れの色が滲んでいる。
「手術したら、しばらくは触れることさえできない。その前に少しでも弾いておきたい」
それは懇願に近かった。
響谷はくいいるようにシャルルを見つめ、オレはシャルルの返答を待った。
「夕方に診察し、問題がなければ考えよう。それまではダメだ。何を言おうと、許可しない。今は休むんだ」
シャルルの声には、有無を言わせぬ力があった。
今更気圧されたわけではないだろうが、響谷の青く澄んだ瞳にさっと影が走り、反論はなかった。
「…わかった」
「少しでもいいから眠っておけ。どうせ機内ではほとんど眠れていないんだろ」
響谷は返事をせずに視線をそらせ、シャルルはしばらくそんな彼女を見つめていたが、ほどなくして部屋を出て行った。
響谷はシャルルの了承が得られないことを予想していたのか、
出て行くシャルルの背を見つめる横顔は無表情だったが、ただ、拳に握り締めた手だけが…かすかに震えていた…………。
オレは気の利いたことも言えず、その青白い横顔を見つめているしかなかった。
響谷はオレの視線に気付いてか、ふとこちらを見たが、何も言わずに自室に引き上げていった。
その後、オレは眠ってしまった為に響谷が何をしていたかはわからない。
夕方、シャルルが診察に来たときには顔色もよかったから、眠っていたのかもしれない。
それでもシャルルの回答は、ノン、だった………。
多忙を極めるシャルルだったが、朝だけは必ず毎日オレたちの様子を見に来た。
オレの手術を翌日に控えたその日の朝、シャルルはいつもと同じようにオレたちを診た。
「予報どおりの天気だな。和矢、昼食を済ませたら薫を温室に連れて行ってやってくれないか。
ヴァイオリンの練習以外はずっとベッドに縛り付けているからストレスも溜まっているだろう。
車椅子を使ってもらうけど、それでも外の空気が吸えるなら、彼女の気分も変わる」
「了解」
昼食をとり終えると、約束どおりオレたちはバラ庭園に向かった。
風もなく雲ひとつなく澄み切った空から太陽の光が暖かく差し込み、確かにこの季節のパリらしからぬ天気だった。
地球温暖化、なんて難しい話を抜きにすると、こんな天気は歓迎だ。
ゆっくりと車椅子を押しながら、バラ庭園を進む。
冬の終わりなので、花など1つもさいてはいないが、庭園は美しく整備され、ところどころにブロンズ像が配置されていて、
花が咲いていなくても充分に見ごたえはある。
温室ではバラが見頃を迎えているが、響谷が外の空気を吸いたいというので、結局花の咲いていない庭園を散歩している。
そこで、初めてお互いがモザンビークでどうやって暮らしていたかを語り合った。
オレは難民キャンプを回りながら情報を集めていたことや、そこで出会った人たちのことを話した。
もちろんガイに出会った時のことも、ケガをしたときの状況なども。
最初に響谷がモザンビークにいると知った時は、驚いた。
自分がこの目で見てきた惨状は、とても彼女の身体と精神で乗り切れるようなものではないと知っていたからだ。
常に危険と隣り合わせという緊張感、小規模な戦闘から逃れながらの生活は体力とともに気力をも奪った。
支えていたのは、シャルルを探し出すという信念のみだった。
何度もくじけそうになった。オレでさえも。
病を抱える女の身で、乗り切れたほうが不思議だった。
響谷が噴水が好きだというので、進路を変えて、バラ庭園を西に向かう。
館内と同じように、ガーデンも殆どがバリアフリーになっていたが、
バラ庭園を抜けて噴水のそばへ行こうと思うと、階段を登るしかなかった。
響谷は車椅子から立ち上がり、白のカシミヤの膝掛けを無造作に車椅子に置いて、ゆっくりと歩き出した。
「ガイの父親から紹介してもらった赤十字の職員を通じて、向こうで活動している日本のNGOに協力していた。
そのNGOと行動を共にしながら、シャルルを探していたんだ。
難民キャンプでこどもたちに音楽を教えながら、シャルルを誘拐したグループに関する情報を収集していた」
オレは響谷の話に耳を傾けた。
低い声で静かに語られる、モザンビークでの様子に。
「あたしが居たのは比較的安全な地区で、NGOの職員に囲まれていたけれど、それでも酷いものだったよ」
視線を足元に下げて、ポツリと響谷は言った。
長い睫毛かかすかに震え、青く澄んだ瞳に影を落とした。そこには緊張の連続だった生活と、
それを不安に思っていたであろう彼女の心境が透けて見えた。
「何人ものこどもを、見送った………。手のない子も、足のない子も、沢山見てきた…」
オレは、彼女の言葉に自分の見てきた光景を思い浮かべた。
全く同じ光景を見てきた。日本で暮らしていれば、全く想像もつかない惨状。
目を閉じると、激しい銃撃戦の音が聞こえてくるようだ。
「病院と言ったって………」
ふいに声が途絶えて、伏せていた視線を上げると、響谷は少し前かがみになり、荒い呼吸にその肩を上下させていた。
耐えかねたように崩れ落ちる身体を、オレは抱きとめた。
「響谷!?どうした!?」
華奢な肩に手を掛けて覗き込むようにしながら、オレは思わず大声を張り上げた。
「………大丈夫………」
深呼吸を繰り返しながら、響谷は応えた。
「シャルルを呼んで来る、待ってろ」
駆け出そうとしたら、腕をとっさに掴まれて制止される。振り返ると響谷はかすかに首を振った。
「少し休めば問題ないから…」
言って、キュッと唇をかみ締める。
オレはあそこまでシャルルが響谷の身体を気遣っているか、今更ながらに理解した。
会話しながらの散歩さえ、今の彼女の身体には堪えるということだ。
オレはそのことに考えが至らなかったことに後悔した。
「悪い、気付かなくて…」
薫の身体を支え、噴水の側のベンチに導く。
「大丈夫だ、気にするほどじゃない」
苦笑に唇を歪ませ、何でもないように言ったが、ベンチに身体を預けるその様子は辛そうだった。
噴水の石垣と一体化したベンチの冷たさも気になった。今日は暖かいとは言っても、
水の近くは思いのほか寒く、服を通してベンチの冷たさが身にしみる。
きっと、彼女の身体にもよくないはずだ。
いつも薔薇色に染まっている唇が、紫色になっている。寒いのだろう。
こんなことをしていたら、風邪をひいてしまう。
「やっぱり部屋に戻って休んだほうがいい。車椅子をもっと寄せるから、待ってろ」
響谷に言い残して車椅子にもどると、オレは響谷に見つからないように木陰に隠れてシャルルをコールした。
幸い、すぐにシャルルは電話に出てくれた。
『どうした?』
発進元が表示されているからか、シャルルは端的に応えた。
『響谷の具合がちょっと悪いみたいだ。今はバラ庭園の噴水のところにいるがすぐに部屋に戻ろうと思う。それでいいか?』
『わかった。すぐに部屋に戻ってくれ。私も部屋に向かう』
詳しい説明をしないオレに、シャルルも説明を求めなかったが、ほんの少しだけ、その声には焦りが含まれていたように感じた。
「部屋に戻ろう。身体を冷やさないほうがいい」
響谷がかすかに頷くのを確認し、まだ荒い呼吸を繰り返す彼女の身体を支えた。
部屋に戻ると、シャルルが既に待っていた。
響谷はバツの悪そうな表情でこちらを睨んだが、オレだって後からシャルルに怒られるのは真っ平だ。
それなら、響谷の機嫌を損ねるほうがマシだ。
「許せ。代わりに一緒に怒られてやる」
響谷の耳元で囁くと、彼女は呆れたような笑みを零した。
オレは車椅子に身を持たせかけている響谷に手を貸そうとしたが、一瞬早くシャルルの腕が彼女を抱き上げるところだった。
オレは響谷が抵抗するに違いないと思ったのだが、意外にも彼女は大人しくシャルルに身を預けた。
シャルルは誤解されがちだが、本当はとても優しくて心配性だ。
こんなちょっとの距離でさえ響谷を歩かせようとしないのは、きっと彼女が心配でならないからだろう。
壊れ物を扱うようにそっとそっと細い肢体を抱き寄せる様子には、そんな彼の気持ちが現れている。
響谷も身体から力を抜いて、まぶたを閉ざし、シャルルに身を任せる。
そのえもいわれぬ緊張感をオレは不思議に思い、そして悟った。
二人は変わったのだと。
シャルルは、突然オレの前に現れていった。
『君の肩の手術をオレにさせてくれないか』と。
それは、グノームの聖剣を取り戻してすぐのことで、まだまだアルディ内での雑務が片付けられるよりも前だった。
目がまわるほどの多忙のなか、それでもシャルルはオレの肩の治療を優先した。
それ以来、シャルルは時に冷淡で時に優美に、以前と変わらぬ笑いを見せる。
はじめのほうこそ、オレは困惑し、緊張したが、すぐに慣れてしまった。
響谷もそうだ。
ぐっと女性らしくなり、以前のように関わることは躊躇われたが、マリナをからかう様子も、
時折口にする痛烈な皮肉も、まるで変わってはいなかった。
でも、違ったんだ。
オレはそう悟った。
以前と変わらないように感じたのは、二人の努力の賜物。
犬猿の仲だったはずの二人の間には、信頼と絆が確かに根付いていた。
それは、二人が互いに傷を抱えながら、幾多の困難を乗り越えてきたかを理解しているからこその関係だった。
オレたちの知らないところで、この二人は想像を絶する孤独と絶望を味わったのだろう。
そう考えると、二人は神々しくさえ思えた。
「無理をするなと言ってあるだろう」
シャルルは響谷をベッドに座らせて上着と靴を脱がせると、そっと肩を抱いて優しくベッドに横たえた。
「もう大丈夫」
「大丈夫かどうかは私が決める。君は黙っていろ」
冷ややかな声でシャルルは応えながら、ベッドの周囲にカーテンを引き、隙間から顔を出して言った。
「終わったらお茶にしよう。和矢、3人分をここに運ばせるように伝えてくれ」
言い終えると、さっと音を立ててカーテンを閉じた。
『酸素は?』
『今はいらない………』
カーテンの隙間から漏れてくる会話。
オレは横浜でのコンサートが終わったときの様子を思い出していた。
あのとき、意識を失うほどの演奏をしたのは、シャルルがいたからだろうか。
シャルルのフォローを信じて、あれほどまで集中することができたんだろうか。
今、彼女が頼るべきは、シャルル………か。
「薬を減らしているから、その影響もあるんだろう。しばらくは安静にしておいたほうがいいが、特に問題はない」
幸い、すぐにシャルルは出てきて言った。
「だから大丈夫だって言ったのに。和矢が大袈裟に騒ぐから」
ベッドの上に半身を起こした姿勢で、響谷はすこし不満げに言った。
確かに本人にとっては慣れたものかもしれないが、彼女の“大丈夫”ほど信じられないものもない。
「診てもらったほうが安心だろ」
刺激を与えない程度に言い返す。
ここで彼女の怒りを呼び起こして興奮させるほど、オレもバカではない。
「どうだか………」
疲労の色がのこる瞳にイタズラっぽい光を浮かべて、響谷は斜めにシャルルを仰いだ。
体調がどうであれ、皮肉だけは言えるらしい。
「そんなことばかり言っていると、お茶を抜くぞ。今日は君のためにスフレを用意しているらしいから」
「あ、そう?それは楽しみ」
嫌味なシャルルの視線をあっさりと無視して、彼女はにっこりと笑って言った。
その姿には、先ほど呼吸を乱し、シャルルに寄りかかっていた姿は見当たらなかった。
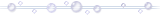
彼女の好物だというスフレ。
今日は、芳しい香りが立つバニラソースのスフレだった。
それを食べてしまうと、響谷はすぐに眠ってしまった。
口に出しはしなかったが、やはり調子が悪いのだろう。
「大丈夫なのか?」
眠る彼女の様子をみていたシャルルに、オレは問いかけた。
「どうだろうね…」
シャルルは、まだ顔色の悪い響谷に酸素吸入をつけて、襟元の毛布を調えると、居間に移動するよう目配せをした。
オレは音を立てないように、シャルルについて部屋を後にする。
「ま、いいとは言えないのは確かだね」
新しく淹れなおされた熱い紅茶を口に含んで、シャルルは全身から力を抜いて言った。
ソファに身をゆだねて、物憂げな表情を浮かべる。
「普段、どんなに言い聞かせても無茶の連続だ。
医者の私から見ても、倒れないことのほうが不思議なんだ。
富士山の上で生活しているようなものだ、彼女の心肺能力ではね。
日常生活さえ、普通に送ることは難しい。それが今の薫の状態だ。
それでも彼女は舞台に立つ。そして完璧を求めて、あるだけの力を注ぐんだ。
でも、無理を通していることは事実だ。
だから舞台が終わった直後に倒れたり、オフになれば高熱を出して寝込む。
それの繰り返しだ。
今回は特に、オフの間に発売するアルバムの製作にかなり力を入れていたようだからね。身体の状態は、良くない」
上品なブルーグレーの瞳に翳りが見える。
それは、彼自身の思うとおりに動かない彼女への苛立ちか、それとも……。
「手術で、よくなるのか」
それは、聞いてはいけない質問かもしれなかった。
けれど聞かずにはいられなかった。
「今よりはね…」
シャルルらしくない、明言を避けた言い回し。
「今より?」
知っておきたかった。
そうでなければ、シャルルがオレを呼んだ意味がない。
オレは気付いていた。
シャルルがあえてオレと響谷の手術を同時に行おうとしたのは、時間の節約のためなんかじゃない。
響谷の為だ。
時間の節約のためなら、響谷の手術を先にしたほうがよほど効率がいい。
一緒に呼んでおきながら、回復に時間の掛かる響谷の手術を後にまわしたのは、
彼女を先にしてしまうと、術後に彼女の容態が急変した際にオレの手術に影響が及ぶからだとシャルルは言った。
そんなことなら、先に響谷の手術をして、容態の安定するだけの時間の余裕をもってオレを呼べばいい。
それをせずに同じ時に呼んだのは、彼女の側に人を置いておくためだろう。
一緒に食事をしたり、散歩をしたり。
そのために、オレを呼んだのではないのか。
ならば、オレには聞く権利があるだろう。
「今のままでは遠くない将来、薫はベッドの上でしか生活できなくなるだろう」
告げられた真実は、想像を超えていた。
「人工心臓の移植を行えば、常人と同じというわけにはいかないけれど、日常生活くらいは普通に送ることはできる」
会話をしながら散歩をすることさえ、ままならない。
この眼でみた彼女が、否定したいシャルルのことばに現実味を与えた。
「ヴァイオリンは、今までと同じように弾けるのかな…」
ヴァイオリンが何よりも彼女の心の平衡を保つのに必要だと思った。
「当面はね」
また微妙な言い回し。
「はっきり言えよ」
「補助人工心臓はあくまで補助だ。彼女自身の心臓にこれ以上の異変が起これば、対応できないこともある。
今以上のことが起これば、それこそもう彼女の心臓はダメだ。
それでも生かそうと思えば、完全型の人工心臓を使うことになるが、おそらくそうなれば彼女は一生を
ベッドの上で過ごすことになるだろう」
今以上の異変…。
それは、いつか起こると確信しているのか。それとも、仮定の話か。
「今後のことはいいや。今、アイツが元気になるなら………それでいい」
君は、バラ庭園が好きだね。
花の季節でなくても、いつも君はあそこに立ち寄る。
思い出があるからか?
そんな思い出は、もう過去のものだよ。
君が帰るのは、ここだ。
バラ庭園じゃない。
君がかえるのは、ここだ。
アルディの人間ではあるまいに、薔薇に還りたいなんて、言うなよ。
バラが好きだというのなら、どんな季節だって、いくらでも君の為に用意しよう。
そう、部屋中が花で埋まるくらい、沢山のバラを………。