〜 3.Like A RoseBouquet 〜
−その日は、オレにとっても緊張だった−
オレの手術の日、まるで自分のことのように響谷は心配してくれた。
もちろん抜釘の手術が大層なものでないことは、誰の目にも明らかだったのだけれど、それでも彼女は心配した。
それはそれは何度も大丈夫かと尋ね、よく眠れたか、気分の悪いところはないかと、コイツがこんなにも
人の世話をやくことが出来たのかと感心するくらいだった。
「自分の心配でもしてろよ」
「自分のことって、どうしようもないっていうか…人のほうが気になるんだよ」
ちょっと照れたようにソッポを向いて、そんな回答だけを寄越してきた。
パリに着いた翌日から、一日2時間程だったが、響谷はヴァイオリンの練習を許されていた。
それも手術の2日前からは禁止で、一日中ベッドに安静の上、心電図やオレにもわからない類のコードにつながれ、
いくつものモニターに監視される生活をさせてられていた。
それでも表面上はいつもとなんら変わりなく………。
手術室に向かう時ですら…。
彼女は、とても平静だった………。
「頑張れよ、待ってるから」
そう言うオレに、響谷は皮肉げにそのバラの花弁のような唇を歪ませた。
「頑張るのはシャルルじゃないのか?」
ひらりと振られた白い指の軌跡だけが、鮮やかに目に写った。
「和矢さま、よろしいですか?」
時刻は21時。
こちらから呼び立てない限り、アルディの使用人が声を掛ける時間ではない。…普段なら。
「どうぞ」
オレが応えると、使用人−カトリーヌが音を立てずに入ってきた。
入り口で立ち止まると、いつもの通り深々と頭を下げる。
オレはその動作さえもどかしく、彼女よりも先に口を開く。
「どうだ?」
こんな時間にカトリーヌが来たのは、響谷の手術のことに決まっている。
予定は決定、それが口癖のシャルルの手術の終了予定はすぎている。
手術中に問題が起こったに違いない。
何が起こったのか…。
容態はどうなのか。
響谷は無事なのか。
結果を聞くまでは、眠れるはずもなかった。
「薫様の手術は、先ほど無事に終わったそうです」
そばかすの散る丸い頬を緩ませて、カトリーヌが言った。
オレはほっとしながら、手元に開いていた本を閉じた。
「よかった…」
「はい、本当に」
彼女は茶色い瞳にうっすらと涙を浮かべていた。
あのとき、アルディに滞在していた際に響谷の専属だったというカトリーヌ。
彼女の苦しみを、彼女の悲しみを、全て見ていたのだろう。
だからこそ涙を浮かべ、その回復を祈る。
「カトリーヌ、良かったな」
とうに勤務時間を終えているはずのカトリーヌにねぎらいの言葉を掛けた。
「はい」
「薫に会うか?」
響谷の手術から3日後。
久しぶりにオレの様子を見に来たシャルルが言った。
まだ彼女は手術室横の濃厚治療室にいる。
思ったより早い申し出に、オレは確認する。
「もう面会しても大丈夫なのか?」
シャルルは手元のカルテを挟んだバインダーを膝の上に立て、そこに上半身の体重を乗せるようにして、
物憂げに溜息をついて見せた。
「いや、余りよくはない。けれどこの数日内に拒絶反応が出るかもしれない…。
だから面会するなら今のうちなんだ」
今が余り良くなければ、拒絶反応が出たらどれくらい悪いのか。
良くないと断言した上で、今面会を勧めるのは、拒絶反応が出ることを確信しているのか。
どれくらいの異変をシャルルは想定しているのか。
不吉な勘繰りが、頭を巡る。
オレは昼過ぎに面会を許されて、濃厚治療室に足を運んだ。
様々なコードにつながれ、酸素吸入をつけて、それでも彼女はベッドを起こした状態でオレを迎えた。
身体はクッションに沈み込むようにもたれかかっている。
全く、自分で身体を支えている気配がない。
顔色も青白く精彩がない。
「寝てなくていいのか?」
また無茶をしているんじゃないかと焦ったが、響谷は落ち着いた様子で首を横に振った。
「リハビリだから、いいんだ。今日は10分間だそうだ」
噂には聞くが、術後は翌日からリハビリを始めるそうだ。
様々な器具に囲まれたまま、身体を起こすところから。
様子を見ながら少しずつ。
「無茶はしないでくれよ。いっつもお前は強がるから」
「今までも、無茶をしたつもりはないよ」
「よく言う」
白々しいセリフに溜息をついた。
一瞬、沈黙があたりを占め、オレはまだ重篤な状態の響谷に叱責ともとれることばを投げかけたことに気付き、
言い方を変えた。
「これでも、結構心配したんだぜ」
オレが言っても、響谷は特に何も返してこなかった。
返しようがなかったからだろうか。
「シャルルの執刀で予定通りに終わらなかったなんて、聞いたことがないから」
さらに言うと、響谷は少し頬を緩ませた。
そして小さな声でポツリと言った。
「兄さんと一緒にさ、散歩をしていたんだ。満開を迎えたここのバラ庭園を…。バラは見事なまでに
美しく咲いていて………」
オレは少し眉を潜めてしまった。
おまえは、今でもそんな夢をみているのか、と。
まだ彼の姿を追い求めているのか。
「だから、ずっとそこにいたかったのに………」
夢見るように微笑む響谷は、幸せそうでいて、どこか危うげだ。
無邪気な優しさを宿した瞳と、甘い砂糖菓子を口に含んでるかのような幸せにほころぶくちびるが、
彼女に潜む翳を際立たせる。
「でも、余りにバラが綺麗で…」
はらりと、彼女の瞳から一筋の涙が零れ落ちる。
「バラに見とれていたら……」
「また、私は兄さまの姿を見失ってしまった…………」
はらはらと、彼女は静かに涙を流し続ける。
見失い、夢の中で彼女はどうしたのだろう。
泣き叫び、その姿を追ったのか。
それとも声を立てずにその場で泣き続けたか。
彼の姿を追わなくて良かったんだとは、軽々しくはいえなかった。
兄さま、きっと小さい頃はそう呼んでいたんだろう。
国立のあの広い庭で、軽井沢のあの別荘で、彼女は兄のことをそう呼んで、いつも一緒にいたに違いない。
彼女が、一番満たされていて幸せだった時代なのかもしれない。
今は、まだ満たされていないのか………?
シャルルやオレでは、マリナでも、おまえは満たされはしないのか………?
はらはらと彼女の瞳からは涙が溢れ続ける………。
オレはその涙を止める術を持たなかった。
「どうした?」
しばらくして様子を見に来たシャルルは、響谷の姿を認めて、哀しそうに笑った。
そっと腕を伸ばすと、神経質そうな白い指で涙を拭った。
同時に反対の手でリモコンを操作して起こしていたベッドを元に戻す。
「泣くと体力を消耗する。しばらくはゆっくりとしたほうがいい。…もう夢など見るな、こちらだけを見ていればいい」
泣くな、とはシャルルは言わなかった。
「夢など、見るな」
重ねて、シャルルは言った。
まるで呪文のように。
毎日、ほんの5分ほどの時間しか許されなかったが、オレは響谷に会いにいった。
たった5分のために、オレはガウンを羽織り、専用のキャップとマスクをはめ、さらに全身に消毒を
浴びなければならなかった。
面会が許されて3日目、シャルルはどうしても外せない用事があるのだと言って、出かけていた。
普段ならシャルルが近くで付き添っているが、その日はスタッフも遠慮してくれたので、オレはしばらくの間、
響谷と二人で話が出来るはずだった。
いつもと同じ14時に、準備を終えて集中治療室に入った。
でも響谷は眠っていた。
薬の作用もあって、一日の半分以上を眠って過ごしているのだから、仕方がない。
彼女の体力と治療の都合から、また後でというわけには行かないので、しばらくの間付き添っていることにした。
眠っていても、傍らに人の気配があれば安心するかもしれない。
痩せたな…。
改めて、思う。
まだ食事は許されていない。
点滴で補給される栄養で足りているはずだが、手術前よりもさらに痩せたように感じる。
顔色は青白くて、いかにその手術が大変なものであったかを物語っていた。
オレがパリを離れるまでに、この部屋から出ることが出来るだろうか。
まだ帰国の日程を決めてはいなかったが、それさえ不安に思わせる寝顔だった。
面会が許される5分の間、そんなことを思いながら、ほんのりと暖かい手を握っていた。
「そろそろ時間です」
スピーカーから退出を促す声が静かに響いた。
オレは響谷の腕に毛布を掛けなおし、出口に向かう。
入れ違いに部屋に入ってきたスタッフに、オレは礼を言うついでに、気になっていたことを告げた。
「すいません、点滴針がささっているところ、かぶれて酷く赤くなっているんです。ちょっと場所を
変えてやってくれませんか?」
軽い気持ちだった。
何度も同じところで貼りかえられるテープで、少しかぶれているだけだと…………。
しかし、オレの一言にそのスタッフの顔色は一変した。
素早い動きで彼は、響谷の医療用ガウンの袖をめくり上げ、腕を診た。
その頬が一瞬にして強張ったのを、オレは見逃さなかった。
彼は続いて幾つも並ぶモニターに視線をはしらせ、小さな声で呟いた。
「GVHDか…!」
その緊張に、オレは響谷に重大な異変が生じていることを悟った。
数日振りにシャルルに案内され、オレは集中治療室に足を運んだ。
直接会うことは叶わず、厚いガラスの板越しの対面だ。
それでも医療用ガウンと帽子にマスク、最後に全身を消毒した上でしか入室を許可されない。
ガラス越しに見る彼女が、最後に見たときよりも、さらに細く小さくなったように感じるのは気のせいだろうか…。
「随分、やつれている」
オレはシャルルを見やった。
シャルルは響谷を見つめたまま、無表情にその薄い唇を僅かに動かした。
「拒絶反応でこの数日間、下血と嘔吐が止まらない…。当然だろう……」
出来うる限りの処置を行っているが、とシャルルは付け加える。
「これ以上続けば、薫の体力が持つかどうか……。生態移植ならともかく、人工臓器の移植で
ここまで強い拒絶反応が現れるのは珍しい」
いつも隠れている額も、耳も、女性のようにすらりとしたうなじも、長い髪を帽子の中に纏め上げた為に、
露になっている。
響谷の病状の説明を続けるシャルルに、オレはやんわりと否定する。
「お前が、だよ」
髪の影がなく、すっきりと露になった青ざめた表情は、生来の美貌も相まって蝋人形のようにも見えた。
シャルルの青灰色の瞳がこちらを見る。
「寝てないんだろ」
確認するまでもない。
いつもと変わらないように見える無表情は、感情を隠しているものではない。
極度の疲労と緊張からきているものだと、長い付き合いで、手に取るようにわかる。
「問題ない」
「少し休んだほうがいい。そのために、医療スタッフが何人もいるんだから」
オレの忠告など、聞く奴でないことは百も承知の上。
「薫は、オレの患者だ」
言い捨てて、シャルルは病室に足を向け、そして立ち止まる。
右手で額を覆うようにして。
言わんこっちゃないと、オレはシャルルに駆け寄った。
「だから言ってるだろ。お前がそんなんでどうするんだ?」
「ただの立ちくらみだ、問題ない」
「休めよ。響谷はオレが見ている」
シャルルの瞳がオレを捉える。
そこにはいつもの物憂げな影は潜め、代わりによく砥いだ刃物のような光が宿っていた。
「君に何ができる?」
珍しく、怒りの色が含まれている。
「オレを信用しろよ」
見返されたシャルルの視線を受け止め、引き寄せる。
「お前の専門は、心理学だろ?精神が身体に及ぼす影響がどれだけ大きいか、お前が一番良く知ってるはずだ」
オレは力強く続けた。
「オレを信用しろよ。部屋の中に入れてくれ」
病室に続く扉に掛けていた手を放すと、シャルルは、震える吐息をついた。
「……わかった」
視線を外して、シャルルは静かに歩き出した。
その姿を見送ろうと、ゆっくりと横を通り過ぎるシャルルの背を追っていると、出入り口の前でその動きを止めた。
「薫は………本当に生きたいと願っていると思うか?」
信じられないセリフに、オレは目を見開いた。
「こんなにも苦しんでまで、ここにいることを、本当に望んでいるのだろうか」
響谷の拒絶反応が、人工臓器にしては極度に酷いものであることは聞き及んでいる。
一分一秒と狂いのないはずのシャルルの手術が、予定通りに終わらなかったことも知っている。
だからと言って………!
オレは、ガラスの板の向こうに響谷がいることも、医療スタッフがいることも忘れ、大声で叫んでいた。
「お前、それ本気で言ってんのか!?生きたいから、あいつは苦しんでるんだろ!?
生きる為に、頑張ってるんだろ!?お前がそれを否定するなよっ」
シャルルが、反射的に振り返った。
まじまじとオレを見つめる瞳は、僅かに潤んでいた。
「あいつを信じてやれよ」
しばらくして、シャルルは溜息とともに呟いた。
「君がいてくれて……よかった………」
「当たり前だ」
シャルルが部屋を出て行くのを見送り、オレはガラス板の向こう側に足を踏み入れた。
響谷を取り囲む機械の音、様々な計器から発される電子音で、その中は意外なほどの雑音に囲まれていた。
音には敏感なはずの彼女でも、今はそれを気にする余裕などないのだろうか。
全く血の気が感じられない顔色。
その中で、口外炎でただれた口元だけがいやに赤かった。
「アルディ博士はお休みですか?」
声を掛けてきたのは、30代半ばの男性の医療スタッフだった。
今の響谷は24時間、必ず医師が付き添っている。
異変が起これば、ナースでは対処できない状態だからだ。
ステンレスのトレーの上に、輸液パックを載せている。
「見た目よりは体力があるようですが、さすがにお疲れでしょうからね」
言いながら、素早く点滴を取り替える。
「確かに、この患者は目が離せない」
薄い茶色の眉を挙げて、そいつは言った。
「僕もずっと心臓外科を専門にしていますが、人工心臓の移植でここまで激しい拒絶反応を示した患者は初めてです」
「何よりも、下血が怖い」
オレの隣の椅子に腰を下ろす。
「心臓に負担を掛けないために、血をサラサラに保つ薬を使うわけですが、それは血小板の量も
減らしているわけです。すると、出血はなかなか止まらない。心臓病の患者はそれが一番怖いんです」
シャルルも、似たようなことを言っていた。
それから、体力を消耗させる高熱も。
手を握ると、いつも冷たい彼女からは想像もできないくらい暖かかった。
「握ってあげてください。あとは気力との勝負です」
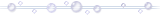
シャルルの献身的な介護のお陰か、数日後、奇跡的に響谷の容態は快方に向かった。
まだ下血や嘔気は完全に収まってはいないが、拒絶反応が収束に向かっているから、いずれ
それらの症状も治まるはずだとシャルルは言った。
「響谷、わかるか?」
オレは呼びかける。
響谷は重そうに瞼を持ち上げた。
「聞こえて、いる」
小さな、機械の音に負けそうなくらい小さな声が返ってきた。
コードが繋がる小さな器具を付けられた手を、一生懸命に響谷は持ち上げようとする。
オレはその手を握る。
「頑張ろうな」
オレは、神は、どこまで彼女に頑張ることを求めば気が済むのだろうか。
骨と皮にしか感じられなくなった軽い腕を彼女は僅かに動かした。
「…大丈夫」
弱い声で紡ぎだすのは、嘘ばかりだった。
やせ細った手を、力を入れないように何度も撫でる。
知って欲しい。魂に刻み付けておいて欲しい。
人のぬくもりというものを。
響谷は知らない。
生気の全くない、いつもの彼女からは想像もつかないような弱々しく潤んだ瞳でシャルルを見上げ、
痛いと、苦しいと、声を絞り出していた。
あの響谷が、痛いと口に出さずにはいられなかったのだ。
想像を絶する苦痛。
シャルルだけが、響谷の涙を受け止めた。
それはシャルルにとっても相当な負担だったはずだ。
治療方針を決め、医療行為を行いながら、さらにその精神的な支えにもなる。
それをオレが見ていたことは、彼女は知らない。
それでいいのかもしれない。
そんな姿を見られることは、何よりも彼女は嫌うだろう。
オレに出来るのは、もっと別のこと。
夢の中ではなく、現のバラを見せること。
現のぬくもりを伝えること。
現の空の素晴らしさを教えること。
現に彼女を呼び戻すこと。
響谷が嘔気を訴える。
吐けない苦痛が彼女を襲う。
シリコンのトレーを口元に押し当て、その背中をさする。
それしか出来なくても。
傍にいてやることなら、出来る。
ひととおりの嘔気が去り、水を含ませたガーゼで口の中を拭ってやると、見る間にガーゼは
口内炎からの出血で赤く染まる。
それでも、ひところに比べれば、嘔気を訴える回数は減った。
響谷はシャルル以外には苦痛を訴えない。
スタッフには敬語で。
オレには軽口で。
『大丈夫』としか、言わない。
それは、余りにも痛々しかった。
彼女の苦痛は、涙は、シャルルにしか見せられないのだ。
「治ったら、シャンパーニュが飲みたいな……」
疲れ果てたようにベッドに沈み込み、青ざめた瞼を閉ざして、響谷は夢見るように言った。
「少し甘くて、口いっぱいに広がる芳香の………ジャックセロスの……エクスキューズがいい」
こんな時でも、アルコールか。
しかも普通では手に入らないジャックセロスときている。
……でも全快祝いにはちょうどいいかもしれない。
「全快祝いに、アルディのセラーを開放させよう」
オレは、響谷のそのかすかな希望の光を必死に掴む。
「シャルルにはオレが交渉してやる」
「そりゃ、いいね。どうせ私が頼んだって、アルコールなんか出しやしないだろうから」
微かだけれども、響谷は声を出して笑った。
笑いながら、眠りに付く。
それでいい。
笑え。
シャンパーニュでもいい。
何かを口にしたいと思えるのは、それは回復の兆し。
夢ではなく。
いつか、現のシャンパーニュを彼女の口に含ませてやる。
それから2週間後、遅れ遅れになってしまっていたが、オレは響谷を残して帰国した。
響谷はまだベッドで寝たきりではあったが、重篤な症状からは抜け出すことができ、オレも新学期が間近に迫っていたから。
日本に帰ってきて、すぐにオレはマリナと会った。
簡単なものとはいえ、手術するに当たっては随分心配もしてくれていた。
今日は、グレーのツィードのワンピースに真珠のボタンが上品な紫がかったピンクのカーディガンを合わせている。
お嬢様っぽい組み合わせは、オレの好みでもあるが、間違いなく響谷からもらった服だろう。
快気祝いとばかりに、オレたちはブフェレストランで色気のないデートだ。
マリナの前には、素焼きの小振りなお茶碗に山盛りのひじきご飯、お豆腐とワカメのお味噌汁、
プレートには出来立てのハンバーグや蒸したてのヒスイ餃子をはじめ、恐ろしいほどの量が盛られている。
かく言うオレのプレートも、結構な量なのだけれど。
「なぁ、お前、響谷に連絡取ってるのか?」
たっぷりの食べ物を前に満足げな笑いを浮かべるマリナに、オレは尋ねてみた。
「薫?そういえば、最近連絡こないわね」
来ない、か………。
自分から連絡するのは、用があるときだけってことか。
オレは半ば呆れながらマリナを見る。
オレたちの再会も唐突なものだった。
マリナの漫画のねたに借り出されたのが始まりだったな…。
「たまには連絡してやれよ」
マリナははじめて目の前のプレートから顔を上げて、怪訝そうな表情を浮かべた。
「どしたの?急に。パリでなにかあった?」
邪気のない表情。
こんなにも純粋な表情をされると、言わないほうがいいような気がしてしまう。
いや、でも告げるべきだ。
「響谷、手術を受けてたぜ」
「え?」
忙しなくプレートと口を往復する箸の動きが止まった。
「まだシャルルのところで入院中だ。まだしばらくパリで療養が必要だと思う」
驚いた様子で顔を上げたマリナと目があった。
「お前も知ってるだろ?アイツの性格。何も言わないけどさ、ああ見えて寂しがりやだから…。
お前からも連絡してやれよ、シャルルに言って、アイツが日本に帰ってくる日を聞いといてやるから…」
マリナは小さく頷いた。
そして一瞬、何かを言おうとしたようだったが、結局何も言わずに、また大口を開けて食べ物を放り込んだ。
何も言わなかったけれど、きっとマリナは響谷に連絡をするだろう。
困ってる奴をほうっておけないのがコイツの性分だ。
気の利いたことはいえないだろうが、きっと、マリナの声を聞くだけでも響谷は元気になるに違いない。
それは、もうオレの知った話ではない。長い二人の付き合いが響谷を解きほぐしてくれるだろう。
今回はこれでお役ごめんだ。
オレは、熱いビーフストロガノフを口に入れた。
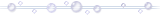
「苦しくは、ないか?」
ハイチェアに浅く腰掛けた体勢で、薫はヴァイオリンを奏でる。
その響きはさらに深みを増したようで、艶やかで甘い音色はこころの隙間に入り込み、そっと癒す。
「全く」
かなりの時間弾いているが、彼女の呼吸はさほど乱れてはいなかった。
薬の影響で少しむくんではいるが、顔色も良い。
軽い足取りで薫は立ち上がり、私の座るソファに歩み寄った。
向かいに腰を降ろし、用意されていたアイスティを口に含む。
立つこともできない程に衰えた筋肉も、日常生活に支障ないまでに回復した。
氷の入ったグラスさえ重そうに見えた腕も、以前と変わらないくらいの筋力を取り戻した。
私が練習時間に制限をつけないでいることに、薫は満足している。
生き残りの激しい音楽界で、薫は常に頂上にいることを望んでいた。
その地位を守っていけるほどの練習量に、今までの彼女の身体は耐えることが出来なかったから。
練習ができない焦燥に彼女はかきたてられていた…。
これからは、自由にヴァイオリンが弾ける。
けれど…。
彼女をこの世に繋ぎとめる手術。
成功することを、本当に彼女は望んでいただろうか。
「復帰のリサイタルには、私も行こう」
「何をプレゼントしてくれる?」
「君は現金だな」
顔をしかめて私が言うと、薫は小さく笑った。
「ではドレスを。復帰のリサイタルに相応しいドレスを贈ろう」
「いや………花がいい」
茎を切られた瞬間から枯れはてることが決まっている、はかない命。
花弁を散らすことが、運命の。
今、ここにいる彼女とは反対の、さだめ。
花弁が散ると、君はそのはかなさに涙するのだろうか?
それとも、羨ましいと………?
「スプレーバラのブーケをシャルルの好みの色で」
「それから、シャンパーニュだったな」
私が返すと、薫は両の目を細めた。
「まさか、本当に許可が下りるとは思わなかったよ」
「和矢との約束だ、君の事よりも私は和矢との約束を守ることが大事だ。
それがいかに貴重なシャンパーニュで、私の趣味に合わないとしてもね」
きめ細かな泡の立つシャンパーニュには、どんなブーケが合うだろう。
少しくすんだ、紫か。それとも、花嫁が持つような純白か。
和矢は飲み逃したと、悔しがるだろうか。
私が選択することはないであろう、比較的新しいメゾン。
アルコールは禁止しているはずなのに、どこからそんな情報を仕入れているのか。
しかし、薫にならば似合うのかもしれない。
あのしっかりした味わいのシャンパーニュも……。
彼女はまた立ち上がり、ヴァイオリンを手にする。
「たまには、リクエストを」
長い睫毛に縁取られた三白眼を甘やかにきらめかせて、彼女は私を流し見る。
「ではショパンのノクターンを。嬰ハ短調 遺作」
私が愛する曲を告げた。
彼女にとって、私がその曲を選択することが意外だったのか、少し驚いたふうに眉を上げて見せたが、
すぐにヴァイオリンを構えた。
伏せられた睫毛の影が、その白い頬に落ちる。
哀しみも苦しみも、全てを跳躍し、彼女は笑う。
彼女をここに繋ぎとめる、悪魔の手をもつこの私にさえ。
今、君が微笑むことが出来るなら、私はいつでも悪役になろう。
そんな私を、君は哂うだろうか。
…………美しい調べが甘美な音色となり、私を包む。
優しく、哀しく………………。
今までは、ノクターンを、自分で弾くピアノ以外では聴きたいと思わなかった。
演奏者にその旋律を穢されているようで。
でも、薫の音は違った。
彼女ならば、薫の音でならば、ヴァイオリンで演奏されるノクターンも悪くない。